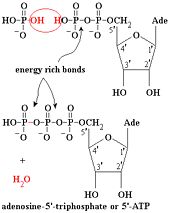
[ATP; Adenosine Tri Phosphate]
アデノシン-5'-3リン酸。アデノシン三リン酸。
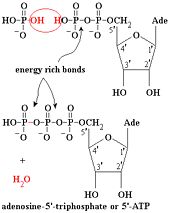
ヌクレオチドの一。
細胞が保存・利用するエネルギーの大部分を占める。
PCrの形で保存されることも。
【特徴】
◆分布
生体内では、ATP濃度はADP濃度の10倍程
骨格筋100gあたり0.4g程度(哺乳類)
イオン・ポンプが脳エネルギー消費の半分以上
(Ames,1997: 17-27)
◆高エネルギーリン酸結合(リン酸基同士の結合)
生体のエネルギー通貨
エネルギー的に不安定で、脱結合でエネルギー放出
エステル結合の加水分解ΔG=-3kcalより非常に大きい
ATP + H2O → ADP + Pi(リン酸)
ΔG゜(標準自由エネルギー変化)= -7.3kcal
ATP + H2O → AMP + PPi(ピロリン酸)
ΔG゜= -8.6kcal
実際はリン酸濃度は標準状態より極めて低くΔG=-10〜11kcal
◆計測
・蛍光分子Syn-ATPで濃度計測(Rangaraju,Ryan,2014)
◆保存
・NaOHやTris(pH7.5)などで中性にして10-100mM
-20度で凍結融解繰り返しても数年もつ
純水溶解の酸性だと37度では24hrsで70%ほど分解される
(「蛋白質・酵素の基礎実験法」)
◆機能
・解糖系…グルコースのリン酸化など
・筋収縮…アクチン・ミオシンの収縮
・能動輸送…イオン・ポンプなど
・生合成…糖新生、還元的クエン酸回路など
・発光タンパク質…GFPなど
・発電…デンキウナギに見られる筋肉性発電装置
・発熱…反応の余剰エネルギーなど
・RNA合成の前駆体
◆反応
・リン酸基転移酵素(キナーゼ)によるリン酸基付加
・ATP合成酵素(酸化的リン酸化、光リン酸化)
ADP + Pi → ATP
・解糖系やクエン酸回路
・GTPからもATP合成
GTP + ADP ⇔ GDP + ATP
・ADPのみでもATPの合成は可能
2ADP → ATP + AMP
・ATPaseが加水分解
◆神経活動
○ATP/bit(情報量)
明順応blowfly視細胞は7e6 ATP/bit (1000bits/sで7.5e9 ATP/s)
(model, 1e6 photons/s: Laughlin,Anderson,1998)
beeでも視細胞2e9 ATP/s(Tsacopoulos,Tsoupras,1994)
視細胞35kとすると網膜で6.5e-5 mls O2/min消費の計算
(実測値は6e-5 mls O2/min: Hamdorf,Wiegand,1988)
視細胞は光子捉えるため細胞大きくRN低いので効率悪め
convergence受けるLMCでは9e5-3e6 ATP/bit
(model, IClに必要なpump流: 1600bits/sで1.4-4.1e9 ATP/s)
一因は高RNと高い情報量/s
spike出すようにしても9e5-9e6 ATP/bit
(この細胞の場合9e6 ATP/AP: van Hateren&Laughlin,1990)
(一般に1-10bits/AP: Rieke,Bialek,1997)
シナプス当り(1320個)では2-6e4 ATP/bit
(55 bits/s(文献)で、1.4-4.1e9/1320 ATP/s)
preはあまりATP使わないと想定
(伝達物質uptakeとrefill併せてもpost電流の<10%)
(ICaとCa pumpではpost電流の2-60%)
(vesicle recyclingは不明)
240小胞/sでもpost電流位の消費には3e3 ATP/小胞も必要
小さい情報容量(小さいN)ほどATP/bit小さくすむ
並列処理の重要性(Laughlin,Anderson,1998)
cascadeがあるとき一般に最終過程(イオン流)でcost最大
(Laughlin,Anderson,1998)
○Na/K より小胞サイクリングでずっと多く消費される
(Rangaraju,Ryan,2014)
APでむしろATP増大する
[Ca]oなしとMunc13-1,Munc13-2のshRNAやTeTXでATP増大
【構造】
◆アデノシン
プリン塩基であるアデニンに糖のリボースが結合
◆リン酸基
リボースの5'ヒドロキシル基に結合
2013/01/28 masashi tanaka