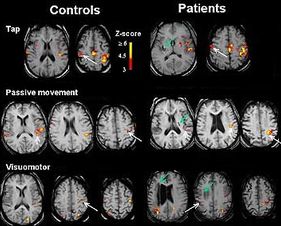
[functional Magnetic Resonance Imaging; functional MRI]
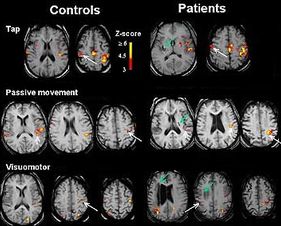
機能的磁気共鳴影像法。機能的MRI。
PETとともに脳機能イメージングの中心的手法。
脳 の活動とMRIの信号値が相関することが1991年に報告されてから、PETに代わる技術として広く使われ始めた。
類似の血流量を測定する方法にNIRSがある。
【分類】
◆DTI(diffusion tensor imaging; diffusion MRI)
拡散テンソル画像(voxel size = 2-3mm)
diffusion-weighted imaging (DWI)
神経細胞レベルでの構造機能解析(微細白質構造解析)が可能
・Diffusivity measures
・fractional anisotropy (FA)
0-1: isotropic(水など)-anisotropic
髄鞘密度・軸索密度など高いとFA高い
crossing fibersが多いとFA高くなる問題
・apparent diffusion coefficient (ADC)
白質などで小さい値、水などで大きい値
・mean diffusivity (MD)
・axial diffusivity (AD)
・radial diffusivity (RD)
◆事象関連fMRI(event-related fMRI)
瞬間的な刺激(事象)でも一定のMRI信号の信号変化
複数刺激へのヘモダイナミクスの重なりも分離可能
【測定法】
◆血流量の増大
神経活動
局所脳血流量(rCBF)が50%以上増加
まず酸化ヘモグロビンの数が増加
酸素消費量の増加は5%程度(Fox et al.,1988)
約6秒後にMR信号が最大
◆BOLD効果(Blood oxgenation level dependent)
(ヘモダイナミクス hemodynamics)
ヘモグロビンは、酸素との結合状態によって磁性が変化する
・酸素化ヘモグロビン (反磁性)不活動部位
・脱酸素化ヘモグロビン(常磁性)活動部位
周囲の水分子は磁化率の違いを受けて緩和が早まる
【特徴】
◆利点
・非侵襲性
・高空間分解能(約1mm)
・高時間分解能(数秒以下)
・高再現性
・高感度(数回程度の加算で十分)ERPやMEGよりはるかに高い
◆問題点
・高い偽陽性(Eklund,Knutsson,2016)
一般的なソフトであるSPM, FSL, AFNIでも生じる
◆inflow効果
比較的太い静脈で血流量や流速の増加すると、MR信号増大
◆解析
・parcellating of cortical network
(Wig et al.,2013; Laumann et al.,2015; Wang,Liu,2015)
個人の脳活動を、平均脳活動(18部位)と比較して正確に領野決定
lateralizationで右利き左利き判定可能(Wang,Liu,2015)
・voxel decomposition
(Norman-Haignere,McDermott,2015)
・dynamic causal models (DCMs)
(Friston,Penny,2003; Stephan et al.,2008)
・generative embedding(Brodersen et al.,2011)
・抑制
(Klein-Flügge et al., 2013; Meyer and Olson, 2011)
・平均でなく個人データも扱える(Gordon,Nelson,2017)
◆機構
・LFPと強く相関
(Mathiesen,Leuritzen,1998; Logothesis,Oeltermann,2001)
(Viswanathan&Freeman,2007)
関係は極めて非線形(Devor,Dale,2003)
抑制性入力によってはLFPから乖離
(Caesar,Leuritzen,2003)
・ヒト聴覚野で単一神経の発火率と相関
(Mukamel,Malach,2005)
・同期したガンマ振動と相関
(cat視覚野: Niessing,Galuske,2005)
◆coordinates
・Talairach coordinate system
・MNI coordinates (Montreal Neurologic Institute)
(Hupfeld, 2021 )
)
・SPM12 space (IXI549 space)
2008/03/10 masashi tanaka